こんにちは、aki(@restudyblog)です。
前回の更新から半年以上あいてしまいました、すみません…(大反省)

なんと七ヶ月ぶりワン!
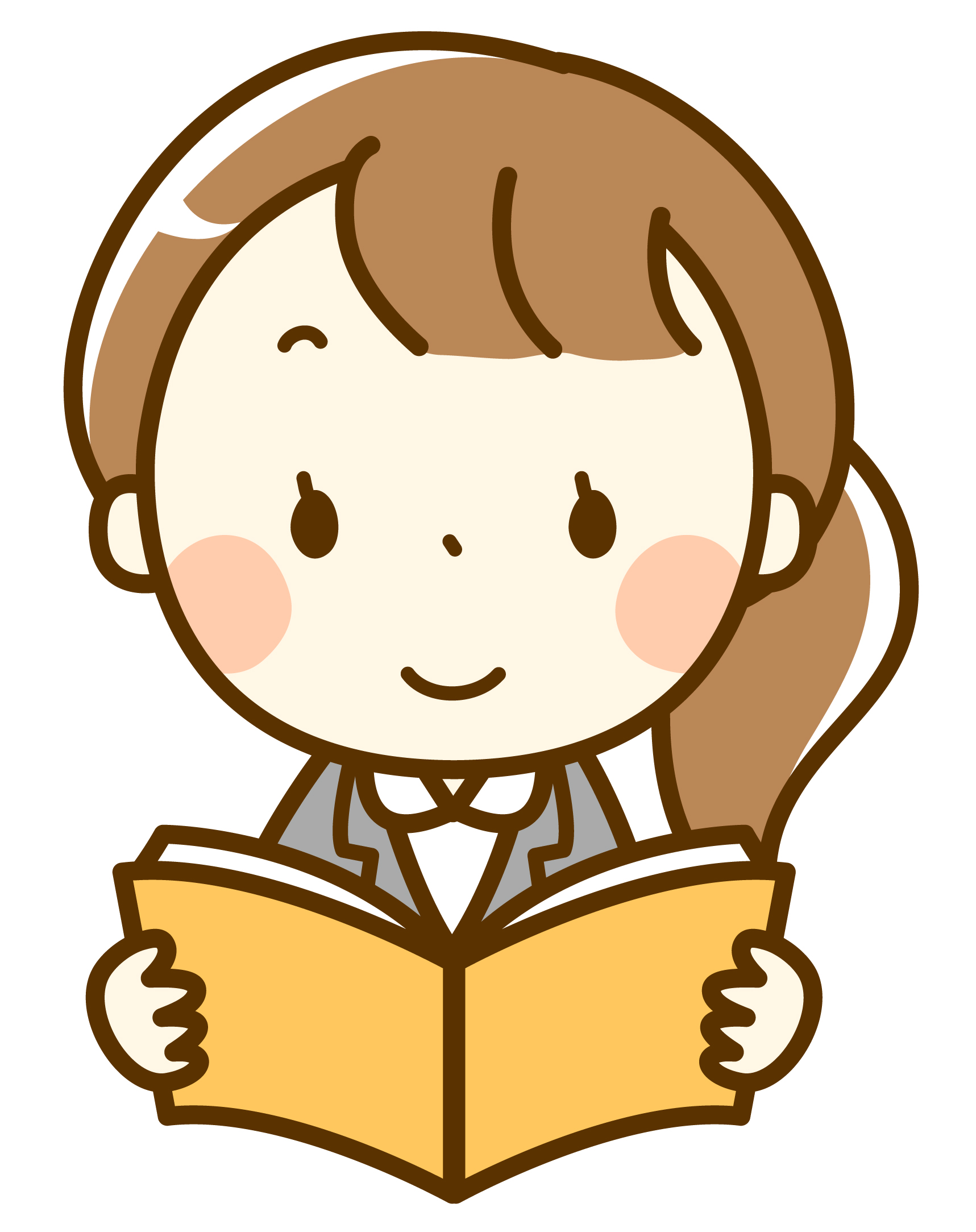
特技のさぼり癖が発揮されてしまい…ごめんなさいw
コロナで2ヶ月ダウン→オンライン診療の便利さを知る
まずは空白の7か月に起こった出来事から。
4月の初めにコロナに感染してから、その後も咳と息苦しさに加え味覚障害の後遺症がしばらく続き、体調が感染前の状態に戻ったのはつい最近の、7月に入ってからでした。
コロナ感染後から1か月ほどは、勉強からも離れていました。

実は、味覚はまだ完全には戻っておらず、地味~に寂しいです。
「感染直後よりはだいぶ戻ってきたかな?」という具合で、以前のようにハッキリ味を感じられる状態にはもう少し時間がかかりそうです。
今回のコロナ感染によって、一度体調を崩してしまうと、
[ 思うように勉強ができなくなる+体調を戻すのにはそれなりの時間がかかる ]
と痛感したので、日々の食事や睡眠、休養など、健康管理がいかに大切かを実感しました
やりたいことをやるためには、土台となる体があってこそなので、今後はほんの少しだけ意識していこうと思います(ほんの少し、がポイント)
今回、オンライン診療を利用してみたところ、すごく便利でした!
家から一歩も出ずに、診察と薬の受け取りができるなんていい時代です。

事前の予約制で待ち時間もほぼなく、自宅にいながらビデオ通話で診察と薬剤師の方からの説明を受けたら、薬は宅配便で届けてもらえます。診察は大体5分ぐらいです。
希望の薬局に処方箋を送ってもらうこともできます。
いくつか利用しましたが「ウチカラクリニック」が良かったです。
オンライン診療だとシステム利用料がかかる病院もあるのですが、「ウチカラクリニック」は利用手数料もかからず、薬の宅配も無料でした(※心療内科のみ、システム利用料が別途かかります)
希望の医師を指定することはできないのですが、担当の先生はしっかり話を聞いてくださったので、安心しました

病院の待ち時間がとにかく苦手でして…今までの傾向だと受付から会計までトータル1~2時間はかかるのですが、オンライン診療だと診察と薬剤師の方の説明時間を合計しても、10分ぐらいです。
緊急を要する場合でなければ、病院にかかる時間を圧倒的に節約できるオンライン診療がおすすめです。
私は今後は基本、検査や病院での治療が必要なもの以外で薬を処方してもらいたい時は、オンライン診療メインにしようと思っています。
特に試験を控えている受験生にとっては、勉強時間の捻出(勉強以外の時間をいかに短縮して勉強時間にあてられるか)も大事なポイントですよね
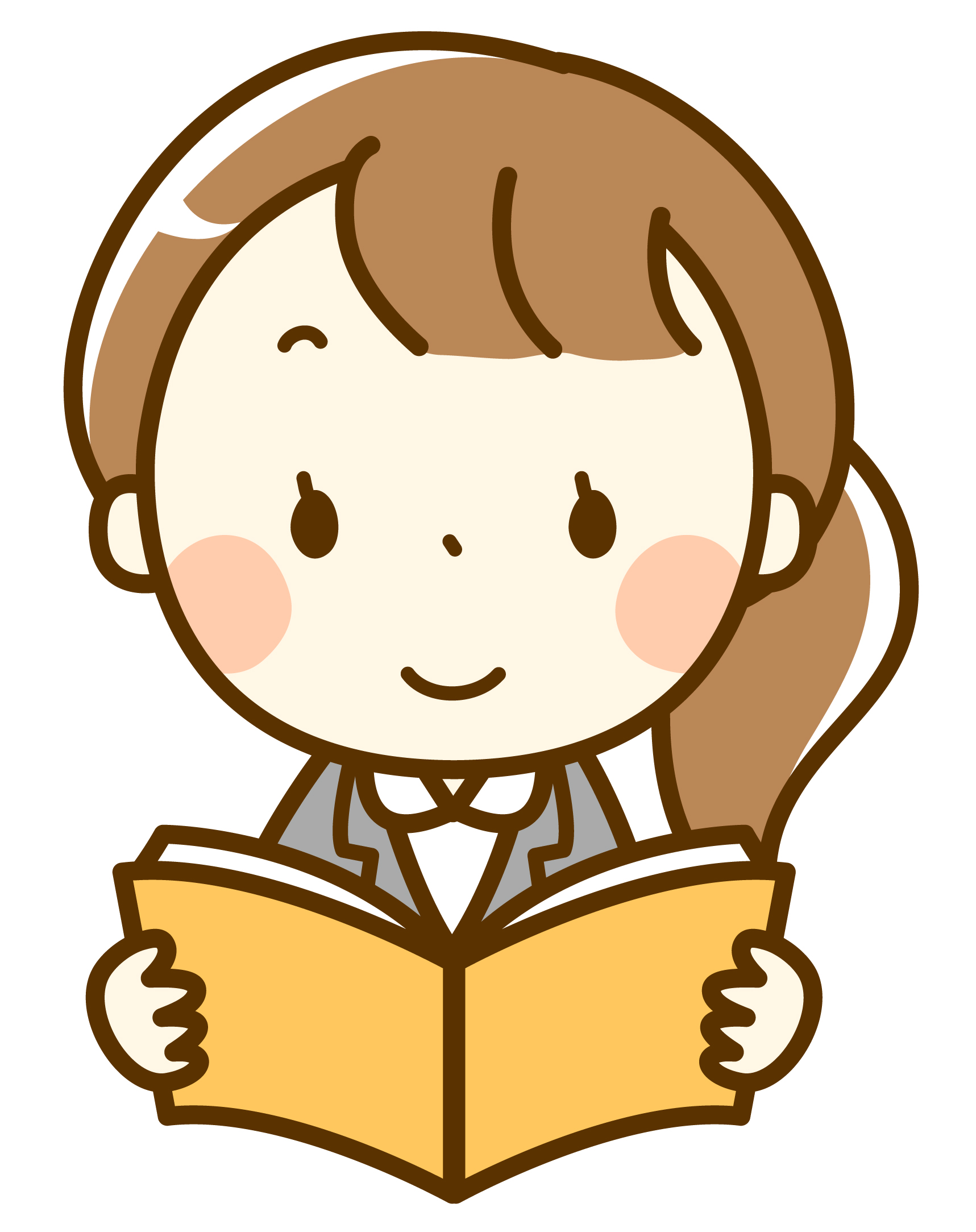
喉の痛みと咳でつらいときには、「エキナケアのど飴」にもお世話になりました

志しただけで全員100点!
さて、本題に入ります。
2025年8月24日(日)に、人生初の社労士試験を受験してきました!
結果について感想を述べる前に、まずは
- 受験することを決意して
- 受験料を振込み(15,000円!高い…)
- 日々、勉強をして
- 当日会場に向かう(会場によっては前泊)
- 着席して30分間、説明を受ける(午後の試験でも30分ある。結構暇w)
- 本人確認時、どんな表情をしたらよいのか迷う(笑えばいいと…略)
- 問題を解く(午前+午後で計290分)
- 突如現れた火サス風の選択肢に動揺する
- 疲労困憊で帰宅
- SNSに思いをぶつける
1つの試験を受け終えるまでの課程に、こんなにも多くの困難が含まれているのです

火サス風!?
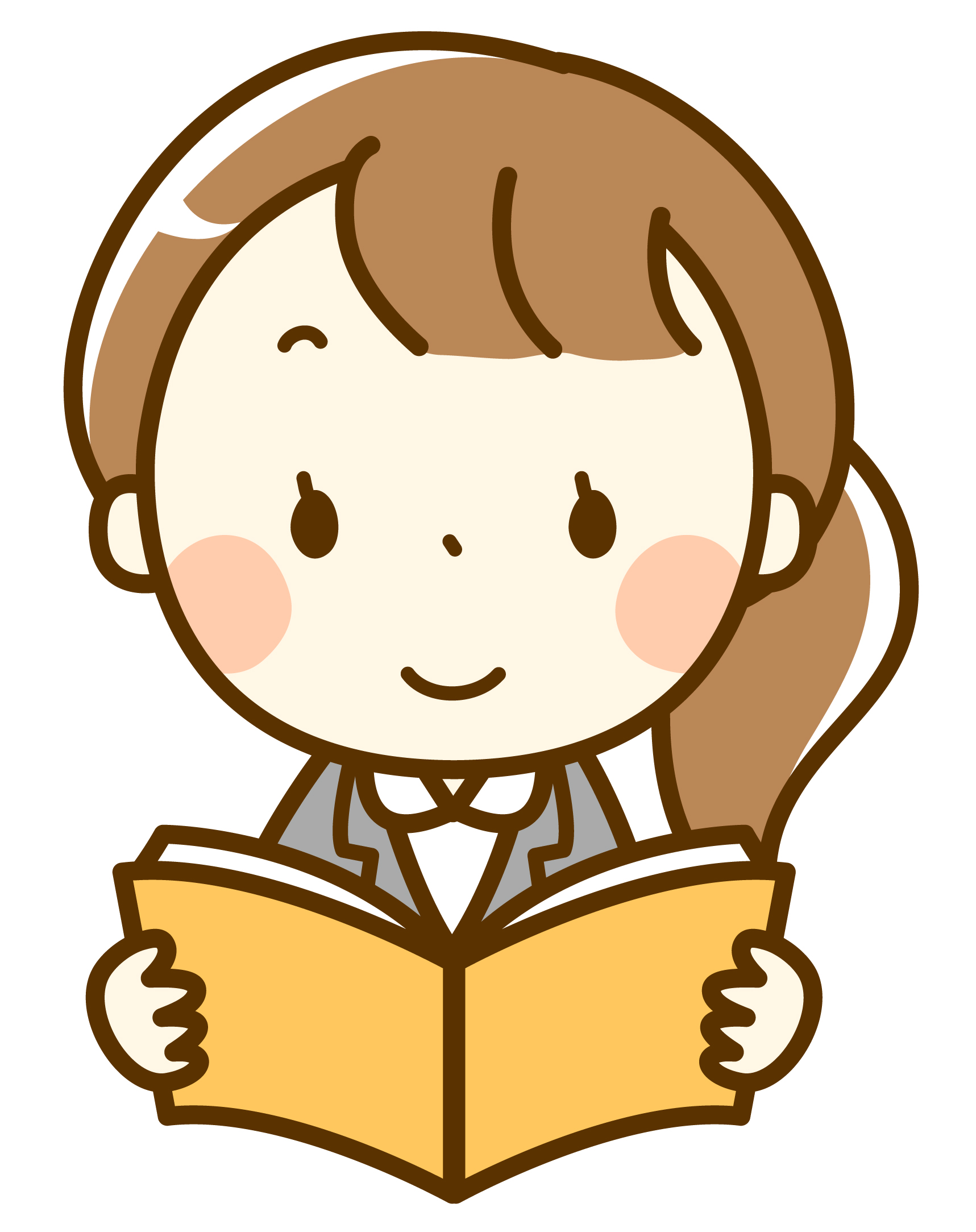
ぜひ本試験問題で確認してみてね!
だからこそ、「受験した」というその事実に、
まずは全受験生(+わたし)に大きな拍手を送りたいです!
皆様、本当にお疲れ様でした☆
もちろん、様々なご事情で当日会場に行くことが叶わなかった方もいらっしゃると思います。
それでもこんなにも過酷な社労士試験を志したというだけで、ものすごーく大きな価値があると思います。
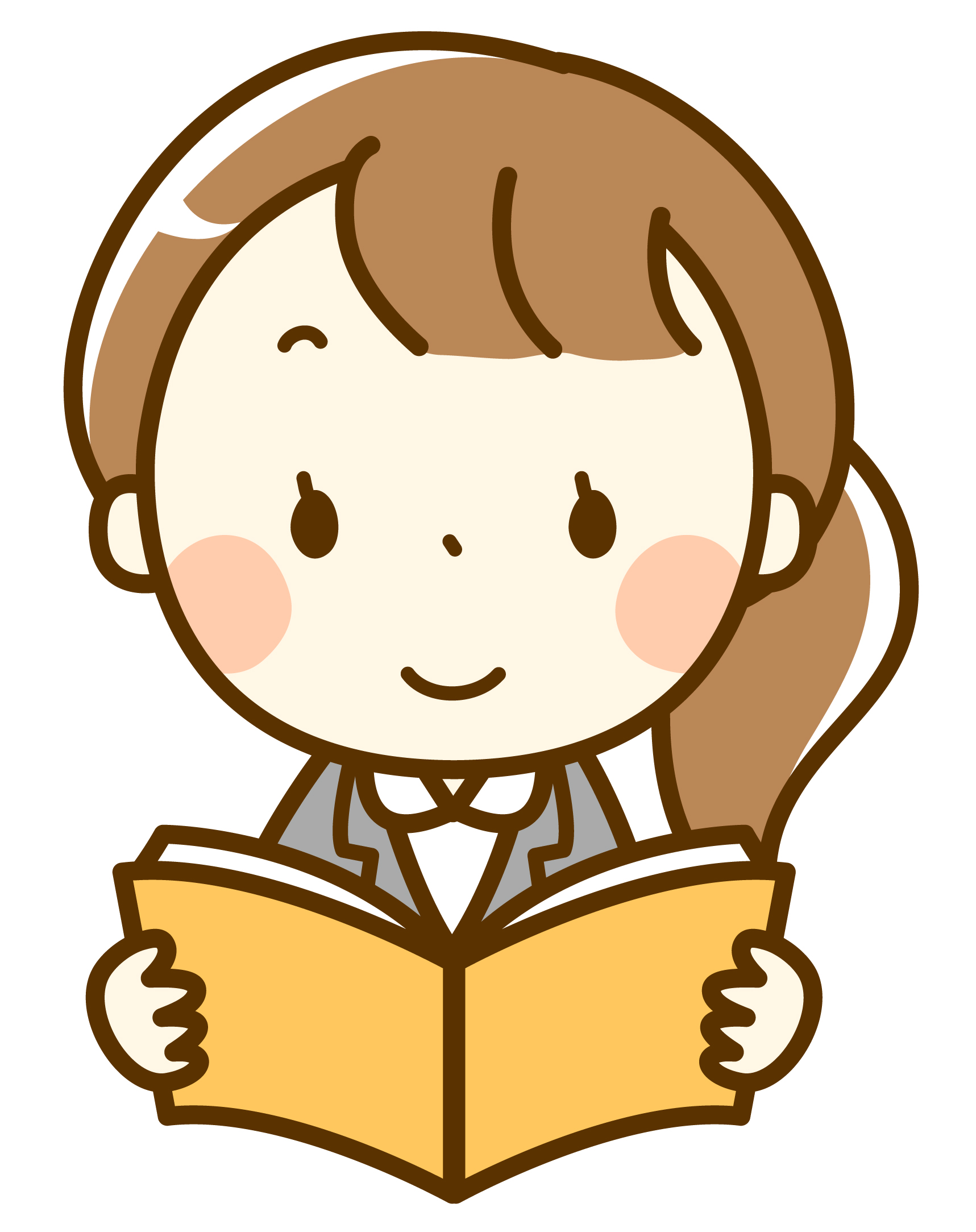
受験を志しただけで全員100点!です

全員に大拍手ワン!
試験会場は東洋大学 赤羽台キャンパス
試験が終わったら、帰宅する前に試験会場の立て札(※「第○回社労士試験」的なアレ)を撮影しようと思っていたのに、試験後はあまりに疲労困憊しすぎて、すっかり忘れてしまいました
試験会場は東洋大学の赤羽台キャンパスでした

申込時は埼玉会場を選択したのですが、どうやら埼玉会場はキャパ超えで、東京会場になってしまったようです。
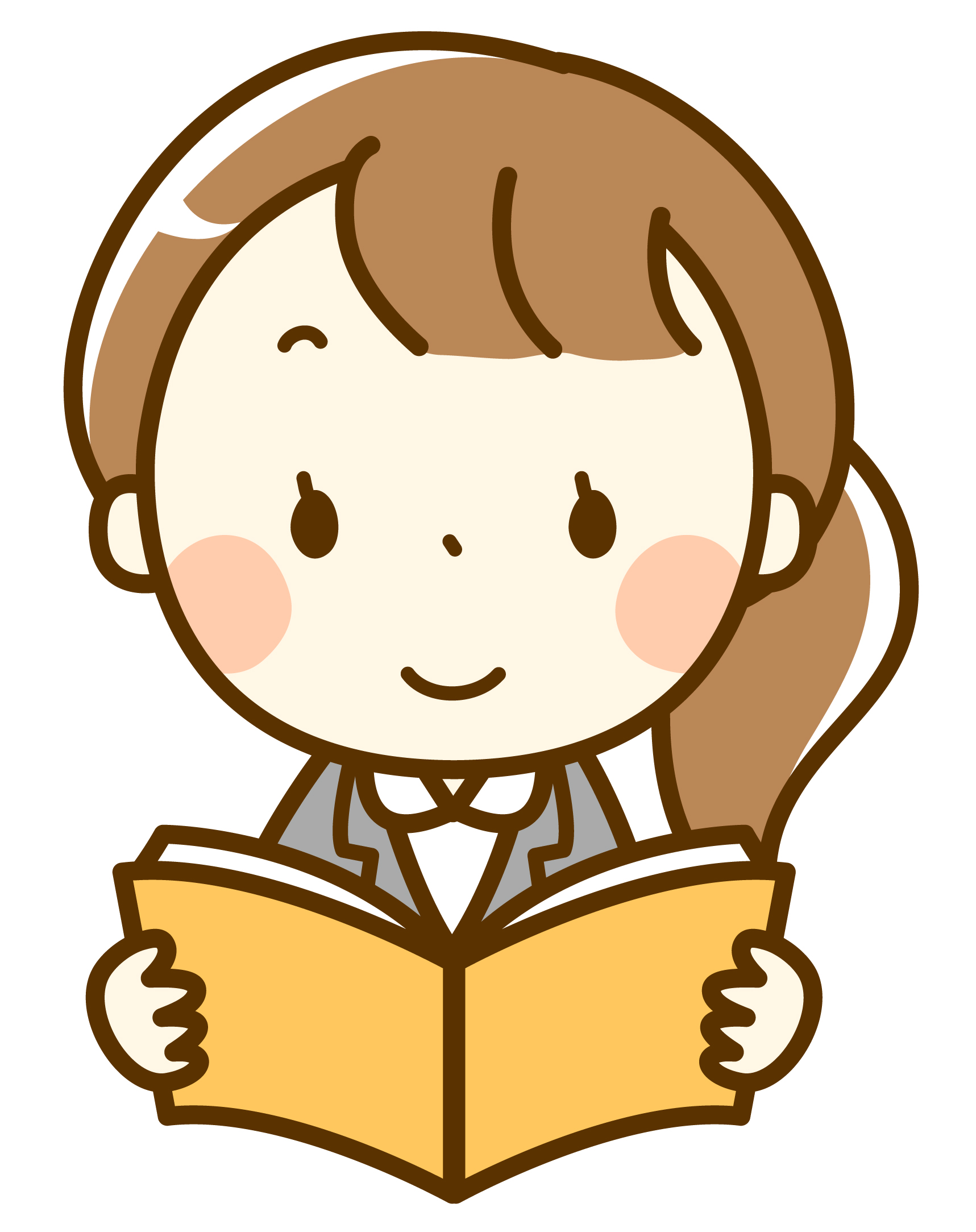
もしくは赤羽は埼玉と思われている!?(違)
結果的には駅チカで綺麗なキャンパスだったので、来年もここがいいかも!と思ってしまいましたw
駅周辺はコンビニはもちろん飲食店も多いので、食事には困りません。
実は、赤羽は高校生の頃に住んでいた家の近くで、よく出没していた町なので、すごく親しみがあり懐かしくもありました。
駅から出たら、すぐ目の前にあるイトーヨーカドーを横目に東洋大学に向かうわけですが、「高校生の頃、このイトーヨーカドーでバイトしていたなぁ…」とちょっと感慨深かったです。

まさかあの頃バイトしていた自分は、40代になって社労士試験を受検することになるとは、全く予想もしていなかっただろうなぁ。
「社労士」という存在すら知らなかった、法律とは無縁だった平和で無知なわたし。
「社労士試験」というものすごく過酷で受験生泣かせな試験の存在すら知らなかった、ノー天気な私…w
私の自己採点結果は…(ここだけの秘密ですよ)
資格の大原の採点サービスで自己採点をしてみたので、公開します。
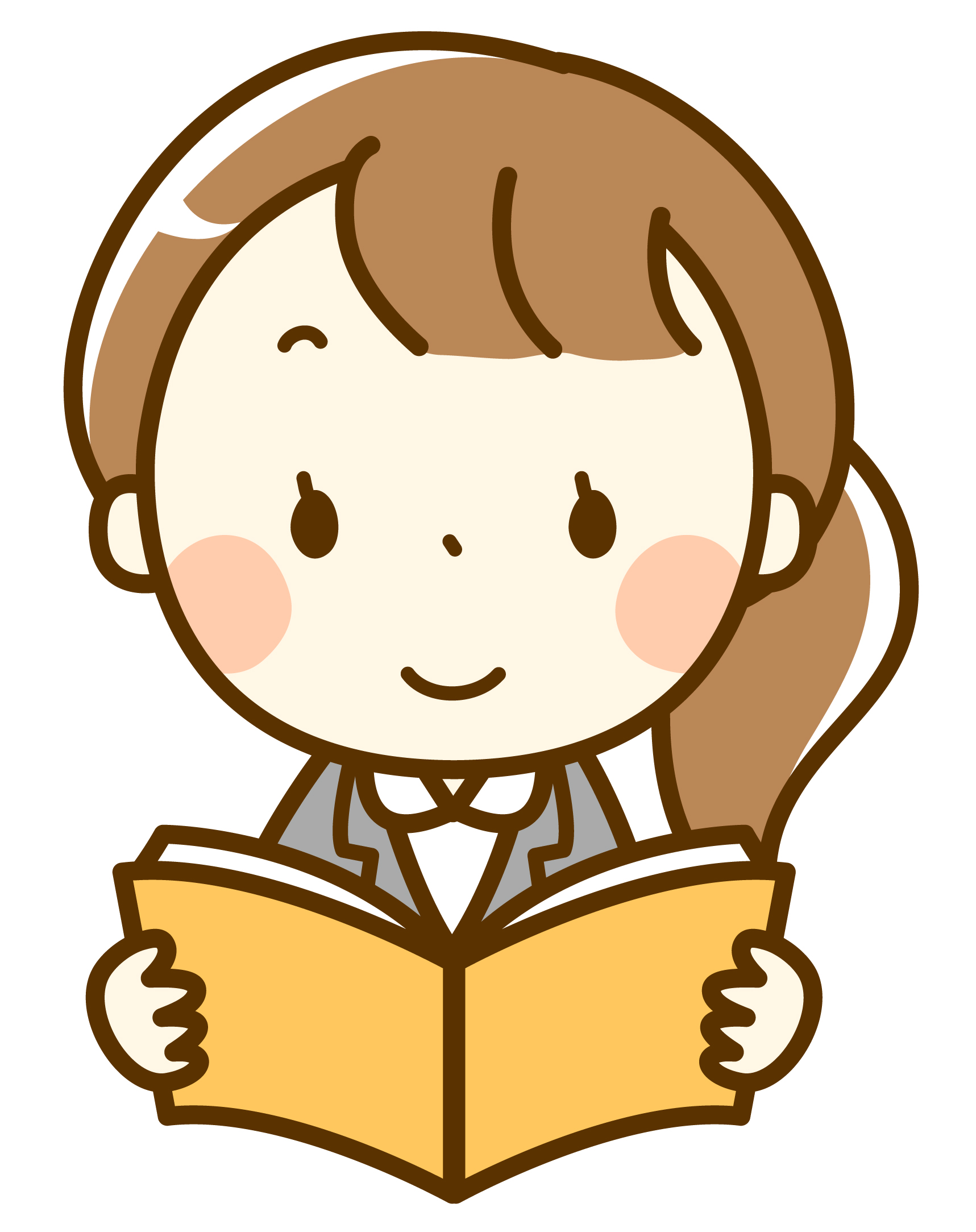
少し画像が荒くてすみません。私の涙でぼやけているのかもしれませんw
※あくまでも自己採点なので、実際の結果とずれる可能性もあります

自己採点の結果は、選択式が27点、択一式が39点でした。
選択式は社一が1点のため、基準点割れしてしまいました。
白書・統計、判例対策は全くと言っていいほどしておらず、社一はテキスト1週しただけで全然時間をさけていなかったのが、如実に結果に表れてますね…
これが現在の自分の、ほぼリアルな立ち位置なんだと思います。
(ちなみに、大原の全国模試では1回目がC判定、二回目がD判定でした…うぅっ)

チャレンジしている証拠ワン!涙をふくワン!
あんなに苦手とする労災と雇用保険が半分以上取れているのが不思議です…
うーん、本試験マジック?(なにそれ)
これといった得意科目があるわけでもなく、「全科目きつくて苦手…」と感じながら、日々の勉強も試験当日も問題を解いていました。
択一では順番に労基・安衛から解いていったのですが、やはり最後のほうは時間が足りなくなってしまい、じっくり問題文を読む時間すらなかった状況で慌ててマークシートを塗りつぶしました。
「次回は、解く順番を変えてみようかな…?」
とも思いましたが、かといって得意科目があるわけでもないのでした~残念!(涙目)
受験する前から、初年度に足りていない反省点はすでにいくつか浮かび上がっていたのですが、受験後に確信(ピキーン!)に変わりました
ザっと思い浮かんだだけでもこれだけあります↓
- 目的条文チェックする
- 判例チェックする
- 毎日年金
- 統計・白書対策する
- テキスト読み込み
- 過去問を解く
- 時間を意識して、回転する
目的条文にいたっては、試験数日前に初めて勉強しだすという驚きの遅さでしたが、選択式では、会場に入る直前にチェックしていた雇用保険法から出題されて嬉しかったです。

全くチェックしていない状態だったら、絶対に解けませんでした…
「必ず出題されるかはわからなくても、チェックしていると報われることもあるのだな」と思ったので、目的条文・判例は毎日少しずつやっていきたいです
判例や苦手な社一、統計・白書も同様に、対策をしないと基準点を超えるのは難しいと痛感したので、2年目はなるべく触れる機会を増やそうと思います
2年目の予定:メイン教材はやっぱり「社労士24」
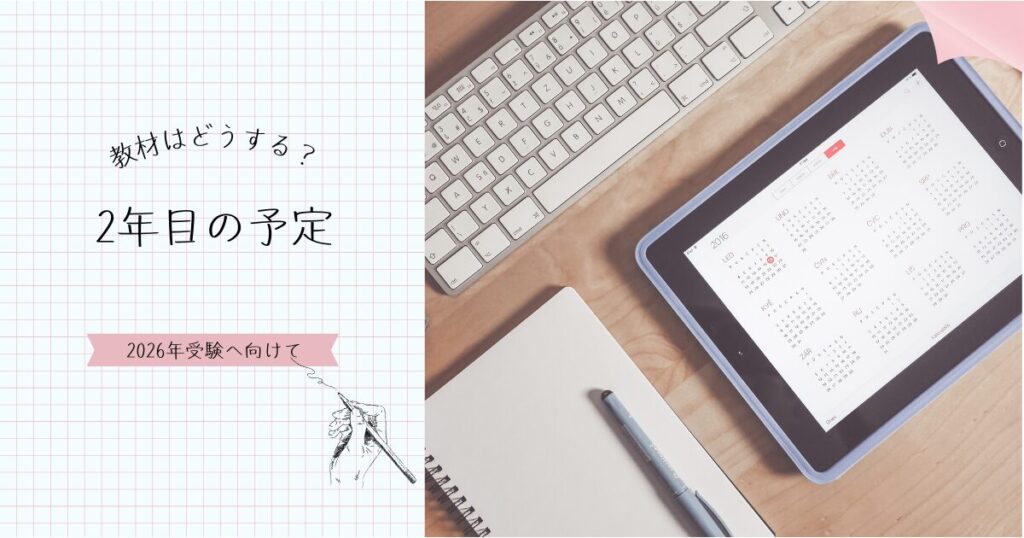
資格の大原の試験講評によると、他の科目に比べて、比較的年金は取りやすい科目のようなので、年金科目を得意科目にできるよう、2年目の勉強は早めに年金に取り掛かろうと思います。
資格の大原には、年金科目を早い時期から学習スタートする「必勝リスタート講座」なるものがあることを知り、
Xで「金沢先生の「必勝リスタート講座」が気になる…」とつぶやいたところ…
なんと金沢先生がいいねしてくださったのです!
これはもう、申し込まないわけにはいかないのですよ。
だって、大原の神講師でもあり、アイドルなんだもん。
ということで、「必勝リスタート講座」申し込みました!
再受講割引(30%OFF)が効くのも嬉しい☆

決断はやっ!!!
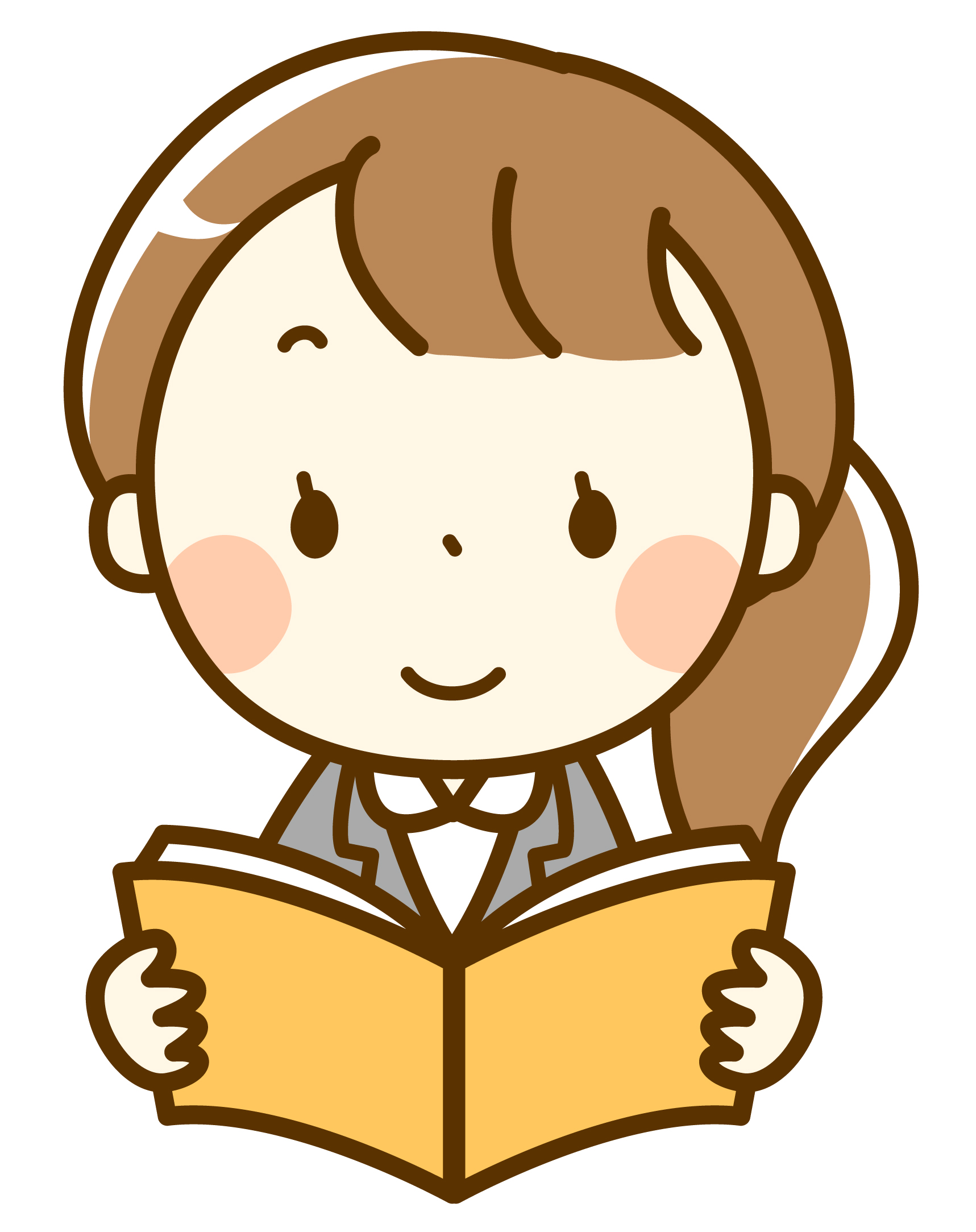
迷いが生じる前に、行動するのがモットーですw
初年度の勉強を進める中で、合格レベルに必要な勉強時間と量が絶対的に足りていないのは自分が一番わかっていたので、受験日前にすでに「社労士24+直前対策」の申し込みも済ませておきました。
そんなわけで、2026年対策用の労働基準法の教材はすでに手元にありますw

はやっ!!!
ということで、
- 社労士24+直前対策
- 必勝リスタート講座
の2つの講座をメインに、取り組んでいく予定です。
引き続き、メイン教材に「社労士24」を選んだ理由はいくつかあります。
一つ目が、とにかく勉強ペース(テキスト読み)が遅い私は、社労士24のテキストの薄さに救われているということ。
他コース(他予備校)の教材だとテキストの厚さは倍以上だと思うので、体力・気力・精神力のいずれもない私には、1周するだけで力尽きてしまいそうな予感がするのです…というより、他の教材だったらほぼ間違いなく挫折していたと思います。
2つ目は、社労士24のテキストが薄い(=ページ数が少ない)ということは、基本事項と重要論点が凝縮されているということだからです。
まずはその基本事項を習得しないと、どんなに他の教材や分厚いテキストを使ったところで、点は伸びない気がします。
ページ数が少ないということは、回転もしやすいです。
今回の試験でもテキスト未掲載の論点が多く出題されている印象ですが、なおさら、テキストに載っている論点をきっちり抑えておく必要があるということだと思います。
それなら、テキストのページ数は少ないほうが効率が良い気がします。
3つ目の理由としては、教材のページ数を少なくするのって、作り手側からしたらとても覚悟がいることで、それなりの根拠や自信がないと難関資格の対策教材として世に出せないと思うのです。
教材のボリュームを厚くすることは簡単ですが、削減することって難しいと思います。
金沢先生が生み出された教材なら間違いないと思えますし、その覚悟や心意気、そしてコンセプトが素敵だと感じます。
というわけで、現時点でのメイン教材は、「社労士24」以外に考えられません。
9月からまたポツリポツリと、自分のペースで勉強はじめていこうと思います。
勉強ペースは遅いかもしれませんが、勉強を楽しむことを忘れないように意識しつつ、たまには趣味の時間も大切にしながら続けていくのが目標です。
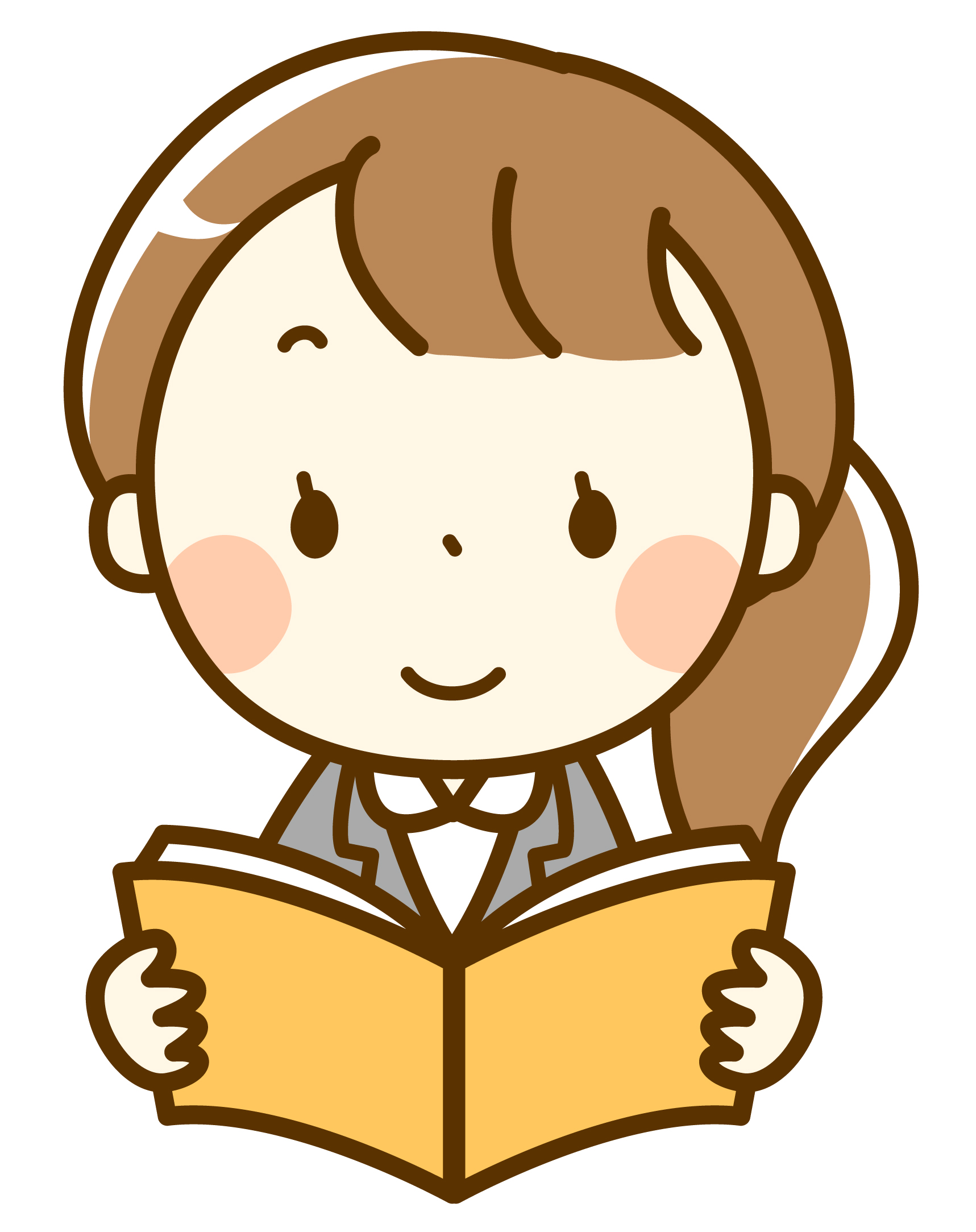
2年目は、高いハードルだけど択一40点超えができたらいいなぁ
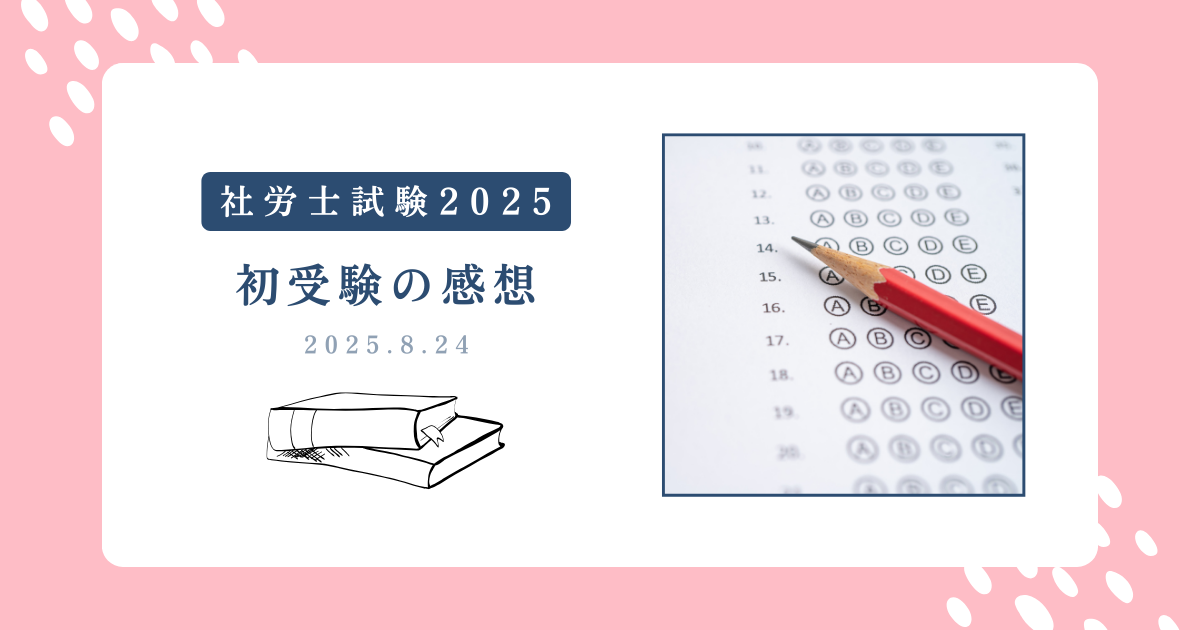




コメント